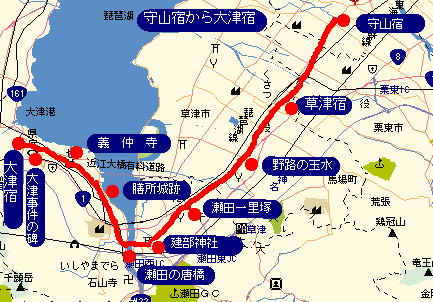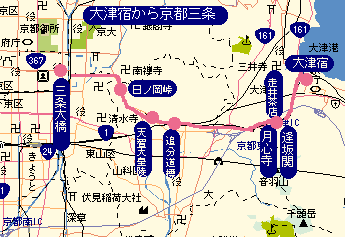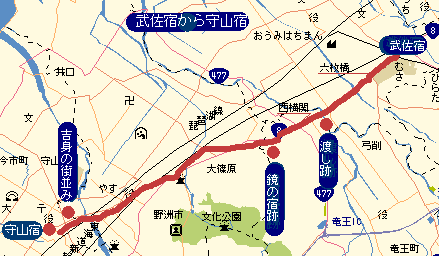
武佐駅から平坦な道を進むと「日野川の渡し跡」があります。平常はこの川を船で渡り、水量が減ると川に杭を打って止めて二艘の船の上に板を渡して船の橋を作って渡っていたのですね。
間の宿場であった「鏡の宿」跡には牛若丸が陸奥に行く途中に元服したという「義経元服の池」や「源義経宿泊の館跡」があります。
守山宿が本宿で「加宿」の役割を果たした「吉身の街並み」をすぎると守山宿です。守山宿には、「宇野元総理の実家」や延享元年(1774年)に建てられた「中山道道標」が残っており「土橋」は広重の版画守山宿風景はこの橋から眺めて書いたと言われています。
「今宿の一里塚」は滋賀県で唯一残っているものです。