|
||
| 西国街道は、西国の大名が参勤交代などで利用し京都東寺まで結ぶ重要な街道で広島藩が特に西国街道とよんでいたそうです。山陽道ともよばれていますが昔の風情を残した所が沢山あります。 | ||
| 広島県内の宿場は10宿で東から神辺・今津・尾道・三原・本郷・四日市(西条)・海田・広島城下・ 廿日市・玖波で街道は国道2号線の近くに残っていますが消えてしまいそうな所も沢山あります。以前から市の教育委員会などが発行された地図を頼りに歩いていましたが、書店で見つけた「梶さんと西国街道を歩こう!」の本を片手に暇を見つけながら歩いてみました。 |
| 広島(元安橋)から東方面(神辺宿)へ歩く |
| 広島から瀬野へ |
| 元安川に架かる元安橋付近は、太田川の水運の便も良く城下町の中心になっていました。立て札が置かれた高札場や馬継場もあり、広島からの里程はすべてこの地点から起算されており、元安橋の側の植え込みの中に広島市道路「元標」(広島県里程元標)があります。 ここからスタ−トし、「本通り商店街」から京橋川に架かる「京橋」を渡り風格のある「猿猴橋」を渡って行きます。橋の名札は、京都に行く方はひらがなで、京都から帰ってくる方は勉強して偉くなって帰ってくるということで漢字になっていたそうですが、猿猴橋はそうなっていますが、京橋は工事の時になにげなくつけたのかそうなっていませんでした。 |
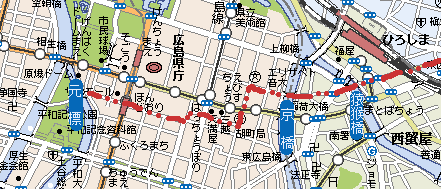 |
 原爆ドーム近くにある元標 |
 |
 |
 |
| 本通り商店街 | 京 橋 | 猿 猴 橋 |
| 豊臣秀吉が街道筋に松を植えさせたと言い伝えがあり古株が3本残っていたので「三本松」と呼ばれ3代目になる街道松の名残や、福島正則に仕え関ヶ原の戦いで活躍した可児才蔵を祀り合格祈願のみそ地蔵の信仰がある「才蔵寺」には数多くの味噌がお供えしてあります。 |
 |
 三 本 松  才蔵寺の石段 |






































 芦田川の川沿いを歩きます
芦田川の川沿いを歩きます




